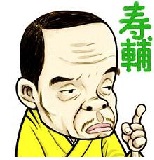京都旅行記2020Ⅱ~天橋立を渡る編~ [日本の旅(京都)]
天橋立の碑が見えたのでスタートしたと思ったのですが、
 あれ、また橋
あれ、また橋
大天橋(さきほど通った廻旋橋は小天橋と呼ばれるんですね)で
小天橋を渡った南東に伸びているエリアと、この大天橋を渡ったところ、
あわせて天橋立。
(ってwikiに書いてありました)https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E6%A9%8B%E7%AB%8B
京都府宮津市の宮津湾(歩いていく方向の右手)と阿蘇海(同じく左手)を
南北に隔てる湾口砂洲。全長3.6㎞。
全体が外洋に面さない湾内の砂洲としては日本で唯一らしいのですが、
京都府の地図(地形)も最近わかってきた私も説明を読んで地図を観てやっと納得。
日本神話にも登場する天橋立ですが、縄文時代、海面上昇で海底に砂洲が形成され、
2200年前に地震で大量に流れてきた砂がたまって海面上に現れて砂洲が大きくなり、
宮津湾と阿蘇海を分離したんですね。
地理もあまり得意ではないのですが(不得意科目が多くて50過ぎてから後悔)
こうやって読むと地形が変わっていく様子は私でも想像できます。
ただ、自然の力で出来たものは自然の力で今も変化しているわけで、
侵食が進んで、昔は弓形だったのが、形が歪んできているので、砂洲上に小型の堆砂堤を
たくさん設置して土砂が流出するのを食い止めようとしているみたいですが、
日本三景と言われるとその維持も大変なのでしょうね。
松食い虫の大量発生や、台風発生時の流木漂着、阿蘇海に大量発生した牡蠣の殻問題、
その他にもいろいろと維持にご苦労されているのをwikiから学習しました。
これから時間の流れとともに自然の形が変わっていくのを人間の手で止められるのか、
止めていいのか、加減の問題なのだろうと思いますが、
自然と人間の共存というのは良いことでもありながら時には良くないこともあるのかも
しれないな、なんて思いました。
 というわけで擬宝珠に挨拶してレツゴ―
というわけで擬宝珠に挨拶してレツゴ―
 見渡す限り松
見渡す限り松
 はしだて茶屋(定休日)
はしだて茶屋(定休日)
開いていたらここであさり丼を食べてみたかったので定休日で残念。
 小雨の中、砂利道を歩いていると
小雨の中、砂利道を歩いていると
大天橋(さきほど通った廻旋橋は小天橋と呼ばれるんですね)で
小天橋を渡った南東に伸びているエリアと、この大天橋を渡ったところ、
あわせて天橋立。
(ってwikiに書いてありました)https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E6%A9%8B%E7%AB%8B
京都府宮津市の宮津湾(歩いていく方向の右手)と阿蘇海(同じく左手)を
南北に隔てる湾口砂洲。全長3.6㎞。
全体が外洋に面さない湾内の砂洲としては日本で唯一らしいのですが、
京都府の地図(地形)も最近わかってきた私も説明を読んで地図を観てやっと納得。
日本神話にも登場する天橋立ですが、縄文時代、海面上昇で海底に砂洲が形成され、
2200年前に地震で大量に流れてきた砂がたまって海面上に現れて砂洲が大きくなり、
宮津湾と阿蘇海を分離したんですね。
地理もあまり得意ではないのですが(不得意科目が多くて50過ぎてから後悔)
こうやって読むと地形が変わっていく様子は私でも想像できます。
ただ、自然の力で出来たものは自然の力で今も変化しているわけで、
侵食が進んで、昔は弓形だったのが、形が歪んできているので、砂洲上に小型の堆砂堤を
たくさん設置して土砂が流出するのを食い止めようとしているみたいですが、
日本三景と言われるとその維持も大変なのでしょうね。
松食い虫の大量発生や、台風発生時の流木漂着、阿蘇海に大量発生した牡蠣の殻問題、
その他にもいろいろと維持にご苦労されているのをwikiから学習しました。
これから時間の流れとともに自然の形が変わっていくのを人間の手で止められるのか、
止めていいのか、加減の問題なのだろうと思いますが、
自然と人間の共存というのは良いことでもありながら時には良くないこともあるのかも
しれないな、なんて思いました。
開いていたらここであさり丼を食べてみたかったので定休日で残念。
ご夫妻の最後の吟遊の旅が天橋立だったことからこの歌碑が建てられたそうです。
与謝野寛の歌は「小雨はれみどりとあけの虹ながる与謝の細江の朝のさざ波」、
晶子の歌は「人おして廻旋橋のひらく時くろ雲うごく天の橋立」と刻まれていますが、
今は自動の廻旋橋も当時は人力だったのを観て詠まれたのでしょうね。
剣豪として名高い岩見重太郎が、父の仇(広瀬軍蔵、鳴尾権三、大川八左衛門)を追って
仇をかくまう京極家の許しを得て天橋立で3人を打倒した現場。
この近くに、仇討ちで使う刀の切れ味を試した石もありました。(写真無し)
岩見重太郎は伝説上の人物とも豊臣家の家臣薄田隼人とも言われているそうですが、
講談でも語られているということなので、探して聞いてみたいですね。
 橋立明神
橋立明神
天橋立神社とも言うそうです。
ちなみにこの近くに磯清水(写真なし)がありました、
塩分の無い水が出る井戸として不思議な名水と喧伝されていたそうです。
ずっと周りに人がいないのんびりした雰囲気で歩いていたのですが、
(松だらけで途中から写真を撮るのもさぼり始めていた)
このあたりで関西弁を話すおばさん2人とおじさんの3人組が大声で話しながら
速足で神社に近づいてきて、その内の1人が特に大声でしゃべりまくっていて。( 一一)
私がのんびり歩いていたのを追い抜き神社で凄い勢いでお参り、
「ねーねー、もう半分くらい歩いているよね?」と一番うるさいおばさんが言っていて
まだ3分の1もきてねーよ、って心の中でどついていたのは私です。(V)o¥o(V)
他の2人が半分もきてないんじゃないの?というと、やだー、そんなにこの先長いなら
もう歩けないー、と言い出したので、心の中で帰れコールを繰り返していたら、
3人Uターンして戻っていきました。ホッとしました。。
 神社の石灯篭がよい雰囲気
神社の石灯篭がよい雰囲気


松に囲まれながらどんどん強くなる雨の中をひたすら歩いて、 阿蘇海側
阿蘇海側

 千貫松
千貫松
名前の通り巨大な松でした。
 芭蕉の歌碑
芭蕉の歌碑
「一声の江に横たふやほととぎす」ってほととぎすが鳴いていたんですね。
この日は雨の音と、自分が歩くときの砂利の音しかせず、
風情を感じる以前に早く向こう岸にゴールしたい気持ちが全面に出ておりました。


 見渡す限り松だらけですが、
見渡す限り松だらけですが、
歩いている途中に、九世戸の松、知恵の松、雲井の松、式部の松、晶子の松、
昭和天皇御手植松、千貫松、阿蘇の松、夫婦松(多分上の写真)、雪舟の松、
なかよしの松、羽衣の松、小袖の松、見返り松、双龍の松、船越の松、
いろいろあると地図に書いてあったのですが、雨がすごくてすべてをチェックする
余裕が自分にはございませんでした。。。。(:_;)
 ゴール
ゴール
多分、これが船越の松だと思います。(多分ね)
お天気がよければ自転車(乗っている人を見かけましたが爆走していました)で
サイクリングするのも楽しそうですが、雨なので歩いたところ所要時間は45分。
地元の人が原付で走り去っていく光景も2回みましたが、歩くのはお天気がよい日に
限りますね。(笑)
とはいえ、端から端まで歩いた達成感は我ながら頑張ったと自画自賛。
この後は、神社を巡ってセットで買った傘松公園にまいります。
(つづく)
この近くに、仇討ちで使う刀の切れ味を試した石もありました。(写真無し)
岩見重太郎は伝説上の人物とも豊臣家の家臣薄田隼人とも言われているそうですが、
講談でも語られているということなので、探して聞いてみたいですね。
天橋立神社とも言うそうです。
ちなみにこの近くに磯清水(写真なし)がありました、
塩分の無い水が出る井戸として不思議な名水と喧伝されていたそうです。
ずっと周りに人がいないのんびりした雰囲気で歩いていたのですが、
(松だらけで途中から写真を撮るのもさぼり始めていた)
このあたりで関西弁を話すおばさん2人とおじさんの3人組が大声で話しながら
速足で神社に近づいてきて、その内の1人が特に大声でしゃべりまくっていて。( 一一)
私がのんびり歩いていたのを追い抜き神社で凄い勢いでお参り、
「ねーねー、もう半分くらい歩いているよね?」と一番うるさいおばさんが言っていて
まだ3分の1もきてねーよ、って心の中でどついていたのは私です。(V)o¥o(V)
他の2人が半分もきてないんじゃないの?というと、やだー、そんなにこの先長いなら
もう歩けないー、と言い出したので、心の中で帰れコールを繰り返していたら、
3人Uターンして戻っていきました。ホッとしました。。
松に囲まれながらどんどん強くなる雨の中をひたすら歩いて、
名前の通り巨大な松でした。
「一声の江に横たふやほととぎす」ってほととぎすが鳴いていたんですね。
この日は雨の音と、自分が歩くときの砂利の音しかせず、
風情を感じる以前に早く向こう岸にゴールしたい気持ちが全面に出ておりました。
歩いている途中に、九世戸の松、知恵の松、雲井の松、式部の松、晶子の松、
昭和天皇御手植松、千貫松、阿蘇の松、夫婦松(多分上の写真)、雪舟の松、
なかよしの松、羽衣の松、小袖の松、見返り松、双龍の松、船越の松、
いろいろあると地図に書いてあったのですが、雨がすごくてすべてをチェックする
余裕が自分にはございませんでした。。。。(:_;)
多分、これが船越の松だと思います。(多分ね)
お天気がよければ自転車(乗っている人を見かけましたが爆走していました)で
サイクリングするのも楽しそうですが、雨なので歩いたところ所要時間は45分。
地元の人が原付で走り去っていく光景も2回みましたが、歩くのはお天気がよい日に
限りますね。(笑)
とはいえ、端から端まで歩いた達成感は我ながら頑張ったと自画自賛。
この後は、神社を巡ってセットで買った傘松公園にまいります。
(つづく)
タグ:京都