金沢旅行記2023~大野からくり記念館編②~ [日本の旅(北陸)]
初っ端から色々説明を長く書いておりますが、
やっと本格的にからくり人形が展示されているエリアにたどり着きました。-4b302.jpeg) 最初は指南車&記里鼓車
最初は指南車&記里鼓車
"指南車"は、中国の黄帝が、強敵が濃霧をもって来襲した時、常に南を指す人形を
載せた車を作り、方向を誤らずに進めたという説話に端を発し、
宋代までの中国王朝では皇帝の行列の先を一里ごとに鼓を刻む”記里鼓車”と共に
進んだと言われています。
指南車の仕組みは磁石によるものと長い間思われていましたが、文献等から
歯車の組合せによる機構を持つ指南車の存在したことが確認されたそうです。
-e37d3.jpeg)
-82eec.jpeg) 指南車
指南車
常に南を指すとなれば磁石を使って方向を探すのかと思ってしまいますが
歯車を使った車というのもからくりの一種ということなのですね。
このような中国から伝わったからくり技術が日本の風習や文化にも取り入れられ、
独自の発展を遂げていく中で祇園会の山鉾に始まり全国へと伝わった山車風流は、
各地で根づいていきますが、尾張地方の徳川家康を祀る東照宮の祭礼を始めとして
からくり人形を中心とした山車祭りが盛大になっているのが今の時代にも伝わって
いるということなのでしょうね。
.jpeg) 現代の職人さんが造った指南車
現代の職人さんが造った指南車
-0b277.jpeg) 顔に表情があれば親近感が増しそう
顔に表情があれば親近感が増しそう
-478df.jpeg) 足元にはからくり
足元にはからくり
-ca172.jpeg) 記里鼓車
記里鼓車
モーターがない時代にこういう機構で車を作るとは凄い(語彙が貧弱)と
思いながら更に先に進むと、木製のパズルコーナーがありました。
-75e74.jpeg)
-d465f.jpeg)
-bcb01.jpeg)
-94050.jpeg) こういうの、苦手です。( 一一)
こういうの、苦手です。( 一一)
触ってフォーメーションを崩して元に戻せなさそうなのでこのあたりはノータッチ。(笑).jpeg) 続いて、職人さん。(の人形)
続いて、職人さん。(の人形)
手前に写っているのが機械時計。職人さんがこれを作る光景のようです。
機械時計は、1551年(天文20年)、宣教師フランシスコ・ザビエルが布教の許可を
得るため、大内義隆に献上したものが日本最初と言われています。
西洋の科学や技術はキリスト教と共にセミナリヨ(神学校)やコレジオで伝えられ、
オルガンや時計、天文機器の製作の授業も行われたそうです。
西洋では、1日を24等分する「定時法」が使われ、規則正しい周期で時を刻む機械時計の
発達によるものでしたが、当時の日本では農業を中心とした社会で、日々形を変える月と
日の長さで決まる時刻制度「不定時法」を使っていたため、西洋時間はそのままでは
役立たなかったそうです。(日が出たら起きて日が沈んだら寝るってことですね)
-4ba48.jpeg) 職人、渋いです(ちょっと萌え)
職人、渋いです(ちょっと萌え) -f29dd.jpeg) ナガス鯨のひげ
ナガス鯨のひげ
今のような人工素材がない頃は自然の素材をうまく使っていたのだと思いますが
鯨のひげってワイヤーみたいな素材として使っていたのかな、と想像しました。
-c69c9.jpeg)
-b3c38.jpeg)
-8996a.jpeg)
ザビエルさんはキリスト教だけでなく様々なものをもたらしたのですね。
と、教科書に載っていったあのお姿を思い浮かべました。
-c7389.jpeg)
-db08b.jpeg) 日高川入相花王清姫ガブ
日高川入相花王清姫ガブ
この「角出しガブ」は特殊カシラの一つで、始めは美しい娘の姿をしていますが、
「小猿」と呼ばれる仕掛け糸を引くことで口が裂け、金色の目を剥き、角が出ます。
これらの仕掛けはみなバネの応用で、バネにはセミ鯨の歯(通称ヒゲ)が、
糸には三味線用のものが使われています。
-7dbd0.jpeg) 鯨のひげ、使われているのですね
鯨のひげ、使われているのですね
.jpeg) 作り方の説明もありました
作り方の説明もありました
-2408f.jpeg) 頭を割る、、、って。(◎_◎;)
頭を割る、、、って。(◎_◎;)
-5f329.jpeg) 江戸時代のお芝居でもからくりが使われていました
江戸時代のお芝居でもからくりが使われていました -f1a45.jpeg)
-92e20.jpeg)
歌舞伎の舞台の模型が置いてあったのですが、場面転換で動き始めました。
-a2546.jpeg)
-b2b43.jpeg)
舞台が回転したと思ったら、
-19d24.jpeg) 福助さんが現れてきました
福助さんが現れてきました
-de088.jpeg)
.jpeg) こんにちは
こんにちは -0431f.jpeg) 「奈落の底」ってここからきているんですね
「奈落の底」ってここからきているんですね -77a67.jpeg) 人力なので重労働です
人力なので重労働です
自分の知っているものが出てきて更に楽しくなってきました。
からくり人形の展示コーナー、もうちょっと続きます。(^-^)
(つづく)
やっと本格的にからくり人形が展示されているエリアにたどり着きました。
-4b302.jpeg) 最初は指南車&記里鼓車
最初は指南車&記里鼓車 "指南車"は、中国の黄帝が、強敵が濃霧をもって来襲した時、常に南を指す人形を
載せた車を作り、方向を誤らずに進めたという説話に端を発し、
宋代までの中国王朝では皇帝の行列の先を一里ごとに鼓を刻む”記里鼓車”と共に
進んだと言われています。
指南車の仕組みは磁石によるものと長い間思われていましたが、文献等から
歯車の組合せによる機構を持つ指南車の存在したことが確認されたそうです。
-e37d3.jpeg)
-82eec.jpeg) 指南車
指南車常に南を指すとなれば磁石を使って方向を探すのかと思ってしまいますが
歯車を使った車というのもからくりの一種ということなのですね。
このような中国から伝わったからくり技術が日本の風習や文化にも取り入れられ、
独自の発展を遂げていく中で祇園会の山鉾に始まり全国へと伝わった山車風流は、
各地で根づいていきますが、尾張地方の徳川家康を祀る東照宮の祭礼を始めとして
からくり人形を中心とした山車祭りが盛大になっているのが今の時代にも伝わって
いるということなのでしょうね。
.jpeg) 現代の職人さんが造った指南車
現代の職人さんが造った指南車 -0b277.jpeg) 顔に表情があれば親近感が増しそう
顔に表情があれば親近感が増しそう -478df.jpeg) 足元にはからくり
足元にはからくり -ca172.jpeg) 記里鼓車
記里鼓車モーターがない時代にこういう機構で車を作るとは凄い(語彙が貧弱)と
思いながら更に先に進むと、木製のパズルコーナーがありました。
-75e74.jpeg)
-d465f.jpeg)
-bcb01.jpeg)
-94050.jpeg) こういうの、苦手です。( 一一)
こういうの、苦手です。( 一一)触ってフォーメーションを崩して元に戻せなさそうなのでこのあたりはノータッチ。(笑)
.jpeg) 続いて、職人さん。(の人形)
続いて、職人さん。(の人形)手前に写っているのが機械時計。職人さんがこれを作る光景のようです。
機械時計は、1551年(天文20年)、宣教師フランシスコ・ザビエルが布教の許可を
得るため、大内義隆に献上したものが日本最初と言われています。
西洋の科学や技術はキリスト教と共にセミナリヨ(神学校)やコレジオで伝えられ、
オルガンや時計、天文機器の製作の授業も行われたそうです。
西洋では、1日を24等分する「定時法」が使われ、規則正しい周期で時を刻む機械時計の
発達によるものでしたが、当時の日本では農業を中心とした社会で、日々形を変える月と
日の長さで決まる時刻制度「不定時法」を使っていたため、西洋時間はそのままでは
役立たなかったそうです。(日が出たら起きて日が沈んだら寝るってことですね)
-4ba48.jpeg) 職人、渋いです(ちょっと萌え)
職人、渋いです(ちょっと萌え) -f29dd.jpeg) ナガス鯨のひげ
ナガス鯨のひげ 今のような人工素材がない頃は自然の素材をうまく使っていたのだと思いますが
鯨のひげってワイヤーみたいな素材として使っていたのかな、と想像しました。
-c69c9.jpeg)
-b3c38.jpeg)
-8996a.jpeg)
ザビエルさんはキリスト教だけでなく様々なものをもたらしたのですね。
と、教科書に載っていったあのお姿を思い浮かべました。
-c7389.jpeg)
-db08b.jpeg) 日高川入相花王清姫ガブ
日高川入相花王清姫ガブこの「角出しガブ」は特殊カシラの一つで、始めは美しい娘の姿をしていますが、
「小猿」と呼ばれる仕掛け糸を引くことで口が裂け、金色の目を剥き、角が出ます。
これらの仕掛けはみなバネの応用で、バネにはセミ鯨の歯(通称ヒゲ)が、
糸には三味線用のものが使われています。
-7dbd0.jpeg) 鯨のひげ、使われているのですね
鯨のひげ、使われているのですね.jpeg) 作り方の説明もありました
作り方の説明もありました -2408f.jpeg) 頭を割る、、、って。(◎_◎;)
頭を割る、、、って。(◎_◎;) -5f329.jpeg) 江戸時代のお芝居でもからくりが使われていました
江戸時代のお芝居でもからくりが使われていました -f1a45.jpeg)
-92e20.jpeg)
歌舞伎の舞台の模型が置いてあったのですが、場面転換で動き始めました。
-a2546.jpeg)
-b2b43.jpeg)
舞台が回転したと思ったら、
-19d24.jpeg) 福助さんが現れてきました
福助さんが現れてきました -de088.jpeg)
.jpeg) こんにちは
こんにちは -0431f.jpeg) 「奈落の底」ってここからきているんですね
「奈落の底」ってここからきているんですね -77a67.jpeg) 人力なので重労働です
人力なので重労働です 自分の知っているものが出てきて更に楽しくなってきました。
からくり人形の展示コーナー、もうちょっと続きます。(^-^)
(つづく)
タグ:金沢
2023-05-14 08:00
nice!(5)
コメント(4)

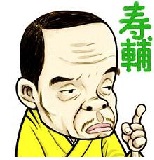





歌舞伎の舞台の模型が面白いですね。福助さんが可愛い♡
by 溺愛猫的女人 (2023-05-14 13:02)
溺愛猫的女人さん、こんにちは。
歌舞伎が栄えたのもこういうからくりで場面転換したりせり上がったり
ということができたのもあるのでしょうね。
by うつぼ (2023-05-14 17:48)
不定時法の方が、人の体にはいいと思います。
畑しているとつくづく。
by 夏炉冬扇 (2023-05-14 18:42)
夏炉冬扇さん、おはようございます。
不定時法は日本が昔から農耕文化だった名残もあるのだと思いますが、確かに人間の体内サイクルに合っているような気がします。(^^;
by うつぼ (2023-05-15 07:42)