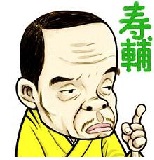青森旅行記2023~たっくんライブ編~ [日本の旅(東北)]
昨年はこの温泉に併設されているホテルに泊まったのですが、
その時知ったのが、「たっくん」でした。
(青森にきて一番の衝撃)https://utsubohan.blog.ss-blog.jp/2022-06-30-2
ライブは無料ですが、ライブ会場にいくためには入浴料を支払わないと、なので、
券売機でタオル(買取)と併せて650円を支払ってチケット購入。
ライブ後にお風呂でもよいのですが先に入っちゃおう、と烏の行水のように
ちゃちゃっとお風呂に入って(化粧が汗で溶けない程度に(笑))から急いで会場へ。
と思ったら、その下に
「大好評の唐揚げは材料の高騰化により一時中止とさせて頂いております」
と書いてありました。国産も輸入もお肉の値段、上がっていますもんね。
鳥の唐揚げは注文が多いメニューだと思いますが利益が出ないのであれば
一時中止、仕方ないとはいえ大好きな方には残念なお知らせですね。
なるべく前方で観たいと意気込んで18:15頃(ライブ15分前)に
休憩用の大広間に到着したら、
Tシャツ着ている姿、初めて観ました。逆に新鮮です。(笑)
と、たっくん横のモニターを見て気づいたのですが、たっくんって、
t9n
って書くんですね。
3文字の空港コード(羽田=HND、成田=NRTみたいな)のような略し方みたいな、
作曲などのクレジットはt9n、歌う時はたっくん、なのかな、と思いましたが謎です。
リハーサルが続いている間、隣のテーブルに中年夫婦と20代くらいの娘さんの3人組が
座ったのですが、スマホを動画撮影用に固定してスタンバイしているのを発見。
家族揃って熱心なたっくんファンなのかもしれません。
でもその横にLOVEのカタマリ。異次元に来た気持ちにさせられます。
今回も
この映像で皆さんも疑似体験していただければ嬉しいのですが、
熱心なファン(動画撮影)もいれば、ほぼ無関心で漫画を読んでいる人もいる、
なんとも不思議な空間でのライブです。
今回、熱唱するたっくんの横のモニターでMVが流されていたのですが。
畑作業するのに上半身裸になる必要はないと思いますが、
鍛えている人が他の人に筋肉を見せたい、会社の他部門のお兄さんも鍛えた筋肉を
インスタなどのSNSにアップしていると聞いたことがあるので、見せたいのだろうな、
そんな気分でマッチョが畑を耕したり野菜を収穫する光景を眺めながら、
たっくんの歌を聞きました。
1曲目は「LOVEのカタマリ」でしたが、
「カッタマリー、カッタマリー」と連呼したかと思うと、
「ラブの国からどんぶらこ」というどこか昭和な歌詞にクスっと笑い、
「ダイコンを引っこ抜く」という歌では、
「大根は長いから畝は少し高くしたほうがいい」
「ちっちゃい大根抜くのは間引きって言うんだよ」という、アドバイスだけでなく、
「大根引っこ抜いて酒飲んだら代行呼べ」という飲酒運転に対する注意もあって、
自分の想像を超えるたっくんワールド(歌詞)を、筋トレ&上半身裸で畑仕事の映像と
ともに楽しみました。
アンコールは前回と同じ「パサージュ広場へ行こう」でした。
終った後、前回と同じようにまちなかおんせんの割引券を配布してくれて、
私もいただいたのですが、上半身ムキムキ(しかも汗だく)のたっくんに
思わず「楽しかったです!」と感極まって言ってしまったら、
(またくるといっても次は来年かなあ。。。)
翌月末までの有効期限なので私は使う機会がありませんが、
記念にありがたく頂戴しました。たっくん、腹筋バッキバキ。
見た目が派手ななのですが歌や態度はとても実直というか素朴というか、ですが、
青森に来る楽しみがお陰様で一つ増えました。ありがとう、たっくん♪
この後は、夜の部に繰り出します!
(つづく)
青森旅行記2023~青森へ向かう編~ [日本の旅(東北)]
青い森鉄道で青森駅に向かいますが、少々時間があったので、
駅に併設されている「三沢駅前交流プラザみ~くる」で時間をつぶします。
ほきのすけ&ホッキーナちゃんに再会した後は、無料Wi-FiでAmazonフォトへ
撮影した写真を同期させたりしていたら、隣のテーブルにいた中国語を話す若いカップル、
言語自体がかなり強めなので最初は普通に会話しているのかな、と思っていたら、
彼女の方が身振り手振りが大きくなって言い合いみたいな雰囲気で(周囲も凍り付き)
彼女が何か言い放ってその場を去っていくのを彼氏が追いかけていく光景が目の前で
繰り広げられて、え、これ現実ですか、と驚いたのですが、
きらく亭での大量ランチ(ビール付)で満腹で眠かったのが、目が覚めました。(^-^;
と、電車の時間まで10分くらいになったので支度して改札に向かいましたが、
去年も見た三沢の名産品コーナーを軽く見学しました。
いか&北寄貝。どちらも好物です。
やはり全体を観ると空港のように見えますね。
ご家族揃っておいで下さい、って書いてありますが、
(しつこいようですが)一人で行っても楽しめます。(^-^;
モーリーと一緒にいるお姉さんは誰なのか、、、不明です。
モーリーの口当たりに顔出し部分があるので大人がやるにはキツソウ。
車内はさほど混んでいなかったのですが、青森の若い方々、、
シートに座らない人が多いみたいで、私が住むエリアだったら優先席でも
平気で座ってお年寄りがきても譲らない若者を時折見かけるのと違う、、
ちょっとした驚きでした。
座席の足元のヒーターがかなり強力でうーん足熱いなあと思っていたのに
気づけば爆睡しておりました。(-。-)y-゜゜゜
JRから切り離されて第三セクターで20周年って凄いですね。
第三セクターなので運賃が高めなのは仕方ないのですが(三沢から1680円)
観光客も楽しく乗れる鉄道でこれからもモーリーには活躍してほしいものです。
Suicaなどの交通系ICカードが使えないのが不便だなあと思っていたので
遂に青森県でも使えるようになれば利便性が上がっていいですね。(^-^)
JALで予約した時そんな注意事項、連絡されていた記憶がないなあ、と思いながら、
スマホで登録しようとしたのですが、スタッフの方の圧が強めでうまく操作できず
(ITリテラシー薄めのおばさん、こういうシチュエーションが苦手です)
「部屋に行ってから手続していいですか」と落ち着いてから手続させて、、、、と
思いながら聞いたら「お部屋に着いて手続きしたらフロントにお越しください」と
言ってくれたのでほっとして部屋に移動しました。
コロナ禍で空いていた時はアップグレードしていただいたこともありますが、
全国旅行支援で満室だと思われ、予約した通りの部屋に案内されるのが通常、
それが当たり前、と思いました。
個人的には延長コードの方が嬉しいのですがベッド近くは電源が見えず、
結局このUSBを使って諸々充電しました。
安いツアーなので恐らくこちら側。反対側だとアスパムとのらくろさんが見えます。
まだ満腹状態(16時ごろ)のまましばし部屋でごろごろしていたら寝てしまい、
起きたら17時半。
急いで支度してフロントでクーポンの手続きをしてもらったのですが、
私がSTAY NAVIで登録する時にチェックボックスを余計にチェックしたらしく、
紙クーポンの発行ができなくなり、電子クーポン用のQRコードをもらいました。
QRコードを読み取るだけで電子クーポン残高が表示されるので簡単でしたが、
ちびちび使うのも面倒なので、この日の夜の部で3000円分一気に使ってしました。(笑)
アナログ世代なのでやっぱり紙の方が安心ですね。
と、色々てこずることもありましたが、この後はお楽しみの場所に向かいます!
(つづく)
登録して電話したら電子クーポンを私が選んだらしく残念。
青森旅行記2023~ホッキ丼で昼酒編~ [日本の旅(東北)]
ホームぺージを見ると米軍の方も利用するショッピングモールのようですね。
とはいえ、現在、一番広いテナントが空いているみたいで笑笑や魚民が入っていたり、
駅から遠い(とはいえ、地方なので車社会で問題ないのかな)のもあって
私のような電車バス移動みたいな人にはあまり便利な場所ではない感じ。
とはいえ、ここのバス停でも観光客と思しきレディース達が乗ってきたので、
観光スポットのひとつなのだと思います。
写真はないのですが三沢駅までの道のりで「勝手貴母」という看板が見えて、
え、なになに、と思ってよく見たら「かってきまま」という名前のスナック。
スナックって不思議な店名(とか女性の名前とか)をよく見かけますが、
バスの車窓から眺める知らない土地の光景、結構楽しかったりします。(^-^)
バスで航空科学館から20分くらいで三沢駅に到着。
駅の反対側に行こうとコロコロスーツケースをもってエレベータに行くと
「ワイヤー凍結のため使用中止」の看板。( 一一)
隣の洗手間は「水道管凍結のため使用中止」となっていました。
雪国ではよくあることなのかと思ったのですが、うちの婆1号のように
膝が悪くて階段の下りが超苦手でエレベータやエスカレータ頼りの人には
こういう便利なものが使用中止というのは一気に不便になってしまいますね。
と書いている私は仕方なく、スーツケースをもって駅の階段をのぼりました。
(スーツケース、機内持ち込みサイズでちっちゃくてよかったです。。)
(食べログ)https://tabelog.com/aomori/A0203/A020303/2000586/
駅前はこのお店一軒しかないので(コンビニもなかったと思います)、
私のような観光客や地元の方々で非常に混んでいます。(土曜日だったし)
お店入口で名前と連絡先を書いておくとお店の方が電話で呼び出してくれる、
というシステムですが、一人なのでカウンターに滑り込めるかと思ったら、
カウンター(時節柄間引き)には地元のおじちゃんたちが座っていて満席。
あとは、4人掛けテーブルがかなり多め、奥には座敷もあって結構広め、
とはいえ、相席にはしていないみたいで各テーブル1人、とか2人、
4人以上だと奥のお座敷、という感じで案内しているようでした。
私も名前を書いて待つこと10分ちょっと。
お店のおばちゃんが私に背を向けてスマホで電話をかけ始めたら、
私のスマホが鳴りました。(笑)
はい、私です、うつぼです、とおばちゃんに背後から声をかけたら驚かれ、
あ、そちらにいらっしゃいましたか、とテーブル席に案内してもらいました。
寺山修司さん(三沢市出身)がの演劇実験室「天井桟敷」のヨーロッパ遠征中、
中華麺が手に入らず細いパスタで作ったラーメンを再現したものだそうです。
(と書いていますが食べていません)
地元の方はカレーライス、とんかつ、ラーメン、中華系(八宝菜)などの
注文が殆ど、ほっき丼を注文しているのはほぼ100%が観光客という感じで
普段は地元の方の食堂兼居酒屋(夜)のようなお店に見えました。
4ヵ月間しか漁をしない(乱獲防止なのでしょうね)ので、
この時期にしか食べられないと思うと注文したくなるのが観光客。
これは以前、青森駅近くで食べたことがありますがごはんにもビールにも
良く合う、モリモリメニューでした。
ビールはキリン、アサヒ、サッポロから選べます。
相席していないので店内そんなにギュウギュウ感はないのですが、
厨房4人、フロアスタッフ2人でフロアの方物凄く忙しそうでした。
「ごはん少なめね~」といいながらお店のおばちゃん、置いていきました。
少なめといいいながら全然ご飯は少なくありません。(笑)
薄切り大根の甘酢漬けと、いかげそともやし、わかめの和え物、味噌汁付き。
三沢市内の飲食店でこの時期ほっき丼が食べられるのですが(マップもありました)
きらく亭さんは2種類の味付けの北寄貝が楽しめます。
長ネギ、椎茸とめんつゆのような出汁でさっと煮たような北寄貝。
極端な話、ご飯一口分であとは、上の具だけで呑めそう、って感じです。
貝の中でも2番目くらいに好きなのが北寄貝(一番は鳥貝)なので、
生でプリっと甘い北寄貝、貝柱まで美味しくいただきました。
地元のおじちゃんがこれとカレーライスを食べているのが美味しそうに見えたので、
思わず注文した私です。(^-^;
なので、ほっき丼のご飯を半分にしてくださいってお願いしたのですが普通盛で。(焦)
ラーメンは期待した通りのあっさり醤油味(鶏ガラ強めな感じ)で、
スープのしみたお麩も美味しかったのですが細めの麺がのびるのが早くて(笑)
先にラーメンを食べて、ちょっとほっき丼、また、ラーメン多めに食べて、
でも、ほっき丼のご飯を残してはならぬ、の気持ちで全部食べきりました。
お腹はちきれそう。(◎_◎;) (夕飯は軽めにしたいと思います)
でも、前回の無念(三沢航空科学館&ホッキ丼)を果たすことができて大満足。
この後は、青森駅まで移動します。
(つづく)
青森旅行記2023~三沢航空科学館編⑦~ [日本の旅(東北)]
己の備忘録としても書いておりますのでこんなに長くなってしまったのですが、
忍耐強く読んでいた皆さまには感謝です。(^-^)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2階の宇宙ゾーンから1階の航空ゾーンに戻り、館内一番奥のエリアに進みますと、
名前は聞いたことがありますが観るのは初めて。
見た目の印象は「お金持ちが乗っているプライベート用飛行機」です。
というか、お金持ちしか買えない飛行機、ですね。(笑)
三沢航空科学館のホームぺージの説明によれば、
本田技研工業が機体とエンジンの研究開発をゼロから始め、
2005年のアメリカ最大級の「オシュコシュ航空ショー」で世界初公開した実験機が
(Proof of Concept)非常に高評価でその後、「HondaJet」の事業化を決定し、
アメリカに「Honda Aircraft Company」を設立したそうです。
wikiによれば2022年2月時点で約200機が運用されているとか。
wikiの説明を観てクスっと笑ってしまったのですが、
設計者の藤野さんがハワイで観たフェラガモのハイヒールから得たイメージを生かした、
先端形状で美しいものを観ていった時に目に留まり応用できないかと思った、
と書いてあって、言われみれば綺麗なフォルム(でも足幅広い人には履きづらそう)、
高級フェラガモのハイヒール(思わずフェラガモのサイトを観に行ってしまった(笑))、
そんなところから着想を得る藤野さんの想像力(創造力)にびっくりしました。
軽くて丈夫な複合材(炭素繊維強化プラスチック)が胴体に使用されているそうで、
胴体の組み立てでは、ハニカムサンドイッチパネルとスティフンドパネルの2種の
構造様式を組み合わせた一体成型技術が採用されているそうです。
と書いている私(文系)はなかなか理解に及ばないのですが、一般的な航空機で
主にアルミニウム合金が使われているのに対し、複合材構造のHondaJetの胴体は、
軽量化だけでなく、NLF技術に必要とされる非常にスムーズな表面形状を実現し、
HondaJetの高い性能に貢献している、そうです。(wikiより転載)
こういう説明を見ていると、航空機メーカーではないホンダならではの着眼点や
発想がこういうジェット機を作ったのかなと思いますね。
と、何だか盛沢山な展示でお腹一杯になったところで今度は外に出ます。
三沢って普段はそんなに雪が多くない地域らしいのですが、
訪れた時はどっさり雪が降った後、という感じで雪の中に飛行機が並んでいました。
F-16戦闘機(一人乗り)。
現代を代表するマルチロールファイターで1974年の原型機初飛行以来、
約4000機以上が生産され戦闘機として優れた能力を有した航空機。
展示されているF-16AはF-16で最も古いタイプA型(米空軍より借受して展示)、
現在三沢基地で使用している機体はF-16CJプラスという最新型。
と書いてありましたが、戦闘機として優れた能力、と読むとどこか複雑な気持ちに
なってしまいますね。闘わずに過ごせるのが一番ですから。
と書いておきながら、折角見学したので説明を観たものはご紹介。
こちらはF-104戦闘機。(一人乗り)
昭和38年(1963年)から航空自衛隊で使用された戦闘機、210機が生産され、
日本全国7つの飛行隊で防空任務に使用され、昭和61年(1986年)に現役引退。
昭和41年(1966年)11月3日、入間基地での航空ページェントで、
東京~大阪間(直線距離で395㎞)を10分21秒(時速2,290㎞)で飛行した記録が
残っているそうです。早い。(◎_◎;)(航空自衛隊より借受して展示)
T-2機。初の国産超音速機で2004年(平成16年)まで航空自衛隊の学生訓練に
使用されていたそうです。
こちらもT-2機ですが、ブルーインパルス仕様。(2人乗り)
航空自衛隊の戦闘機パイロットを養成する最終段階で使用する超音速の高等練習機、
その優れた性能から二代目ブルーインパルス使用機として昭和57年(1982年)から
平成7年(1995年)まで全国で華麗な展示飛行を行ったそうです。
ブルーインパルスというと一昨年の東京オリンピックで都内を飛んだのを思い出しますが、
飛行ルートに足立区が入っていたので、東京と江戸川を挟んで対岸のM戸市でも
見られるかとベランダで待っていたものの米粒サイズの飛行機が飛んでいるように
見える、って感じで終了してしまい、都内の酒友たちが撮影したブルーインパルスの
写真をFBなどで観て羨ましかった、そんなことを思い出しながら飛行機を眺めました。
初の国産戦闘機であるF-1はT-2高等練習機を発展させた支援戦闘機で、
生産ライン上のT-2の6,7号機が原型FS-T2改へと改造され、
昭和50年(1975年)初飛行、F-1量産機は昭和52年(1977年)から計77機生産、
昭和53年(1978年)から三沢基地の第三飛行隊を皮切りに3個飛行隊に配備され、
現在は交代が進んでいるそうです。
日差しで見えづらいのですが(というか個の写真で見えるわけないんですが)、
先頭には「疾風迅雷」の文字と兜に矢、尾翼には兜を被った武将?の絵が描かれています。
P-3。
ロッキード社ターボロップ旅客機「L-188エレクトラ」をベースとして
開発された大型対潜哨戒機。戦闘機ではないのでかなり大きく見えました。
空港のターミナルをイメージしたんでしょうかね、右上には管制塔ぽいものも
みえて外観でも楽しめる場所だと思いました。
一通り見学して約2時間弱。
ハンバーガーが美味しいお店の支店らしいのですが、
私はこの後北寄貝を食べようと思っていたので、このカフェはパスしました。
お土産を買って洗手間ですっきりしたら、
バス停から見えるモニュメントにミス・ビードル号があったのを発見、
(その近くの銅像は飛行士のパンクボーンさんとハーンドンさん)
前回来られなかった三沢航空科学館、機会があればまた来てみたい、
空に関する多くのことを見て知ることができました。大満足。(^-^)
この後は三沢駅に移動して、お待ちかねの北寄貝です!
(つづく)
青森旅行記2023~三沢航空科学館編⑥~ [日本の旅(東北)]
セコムしている金の重さをしみじみ感じた後は、
プーリー(pulley)は滑車ですが、動滑車が2個ついているので1個の場合より
引っ張る力は2分の1で済む、というのは頭の中では分かっておりますが、
まだ完全に左上腕治ってないしなー、という言い訳で(笑)パスしました。
ハンドルを回すことでカムが動いて上下に動くことで設置されたエレベータも上下する、
のですが、以前の勤め先(産業機械製造)でカムについて設計の人から教えてもらったのを
思い出しながら無心でハンドルを回しました。エレベータが結構上がってヒデキ感激。
社会見学でやってきた小学生が被る光景を思い浮かべました。。。
テレビで見てからずっと気になっていたお仕事。
到着した飛行機をパーキングスポットに誘導するお仕事で、
飛行機が停止線でピタリととまるように緻密に誘導、というイメージです。
最近、人ではなくパーキングスポットにデジタル表示されているような機械化が
大きな空港では進んでいるみたいですが、省人化(デジタル化)が進む昨今、
こういうお仕事も徐々に機械化される流れなのでしょうね。
(パドラーって船のパドルから派生した名前なのでしょうか)
コックピットの機長様に見えるように大きくパドラーを合図に合わせて振るので
緻密さに加えて結構腕まわりの筋肉を使う体力のいるお仕事なのだと実感しました。
私自身は、「これもリハビリの一環」という気持でパドラーを振りました。大満足。
続いてコックピット見学。
今は自動化されている作業もあるかと思いますが、これらの計器を操作して
天候や気流を読みながら安全に目的地まで旅客や貨物を運ぶ、パイロットというお仕事、
本当に責任感、判断力が強くないと出来ないお仕事だと改めて尊敬しました。
日系だと大丈夫かなと思うくらい細いお体のCAさんが重たいカートを押していて
心配になる時がありますが、これが米系だったりすると屈強なCAさんがいとも簡単に
カートを移動させているのを昔よく見ていたので(特にウナイテッド航空)、
保安要員とはいえCAさんも体力勝負のお仕事なのだなとしみじみ思いました。
はやぶさ(小惑星探査機)。
太陽系の化石ハンターという呼び方にクスっと笑ってしまいましたが、
地球以外の惑星についても調査が進んでいくのでしょうね。
宇宙空間の無重力状態を体験できる(360度回転するらしい)そうですが、
自分がぐるぐる回る姿を想像したらチャレンジ精神があっと言う間に遠のき、
遠巻きに見学するのみでした。
スタッフの方と目が合いましたが「いかがですか」と声かけされることなく、
おばちゃん(私)の健康を心配して声かけしない優しさを感じました。(笑)
トヨタとの現在共同開発中で、実際の大きさはマイクロバス2台分。
2人乗りで(車内では宇宙服を脱いで作業可能)水素から作り出した電気で走る、
実現すれば、宇宙飛行士の負担も軽減されて探査自体の効率も向上するのでしょうね。
船外作業服ですがものすごくごっつくて重そうでした。
宇宙から降ってくる放射線の1種なんだそうですが、
説明がなければ、箱の中に線が見える、で終わってしまったかもしれません。(^-^;
成虫とさなぎ、たまごを保持、飼育したそうですが、
宇宙放射線の影響を受けたハエを宇宙から帰還後もその影響を調べたという説明に
こういう地道な実験が将来の役に立つのか、、、文系の私には難しすぎましたが
なんとなくそんな気持ちにはなれました。
小型超音速旅客機をJAXAで研究していたのか、と驚いたのですが、
以前実証実験などを行っていたみたいで(コンコルド退役後から2015年まで)
今は研究は止まっているのでしょうか、機体概念として展示されていました。
2階はさほど広くないので(あとは宇宙となるとちょっと難しいと思ってしまう)
あっという間に見学終了し、再び1階に降りて他の展示を見てから館外の展示を
観に行きます。(^-^)
(つづく)
青森旅行記2023~三沢航空科学館編⑤~ [日本の旅(東北)]
写真が多くて(撮った自分が驚いています(笑))おまけに説明が長すぎて
つい記事が多くなっていますが、あと3回くらいで書き終えたいと思いますので、
皆さまも気長に読んでいただければありがたいです。<m(__)m>
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
体験コーナーに進みますが、その前にちょっとだけ未来の乗り物。
最初はリモコンカーみたいなイメージ(おもちゃぽい感じ)だったのですが、
昨今の技術では複数のドローンをプログラミングしてパフォーマンスしたり、
高いところからドローンが撮影することで素晴らしい自然を俯瞰して観ることが
出来たりする一方、軍事用(偵察など)にも使えたりして、世の中便利になると
良いことばかりに使われないこともあるのだなと思う今日この頃です。
(神社仏閣で使用が禁止されているのも理解できます)
Amazonのような宅配でドローンが配達するとか、人を乗せて、みたいな話も聞きますが、
世の中の進歩も出来ることと倫理的なせめぎ合いみたいな中で進んでいくのかな、
という気持ちになりました。
館内、場所柄米軍ファミリーみたいな感じの方々が多かったのですが、
ファミリーの金髪お母さんがこれを体験するのを見学させてもらいました。
ベストを着てそれをワイヤーで接続して水平(うつ伏せみたいな恰好)で
レールにそって館内を滑空する、みたいな体験コーナーで、
体験していたお母さん、物凄く楽しかったみたいで絶叫していました。(笑)
私も体験、一瞬脳裏に滑空する自分の姿を想像しましたが、
おそらく重そう(己)で無理、冷静に即諦めました。(^-^;
ジャイロ、私も聞いたことはありますが、説明の通りにやってみたつもりながら
思ったような反応がなく、おそらくやり方が悪かった、、、、みたいです。
自分の反射神経を測ったことがないのでこれはやってみようとチャレンジしましたが、
光るランプをタッチしたものの、終盤スピードが上がると手がついていけず、
スタッフの方が手持無沙汰に見えたので「これはなんでしょうか」と声をかけてみると
圧縮空気で人間を押し上げる仕組みですという説明を聞いてやってみたくなったものの
「私(巨漢)でも大丈夫ですか?」念のため聞いてみて(笑)、「大丈夫です!」と
答えてもらったので安心して体験しました。6人くらい乗れますが貸切。(^-^;
シートベルトをしめて(荷物は外のロッカーに預けました)両脇の手すりにつかまり、
数十秒だと思うのですが、プシュ―という音と共に上がったり下がったり、
まるで気流の悪いところを飛んでいる飛行機のような、そんなに激しくなかったものの
食べてすぐじゃなくてよかった、、と思いつつ、楽しい体験となりました。(^O^)/
入門とありますが、パイロットになるのって本当に大変なんだな、と思いながら、
と、喜んでいたら、あっという間に東京スカイツリーが傾いて
(傾いているのは自分が乗っているヘリコプターなんですが(笑))
運転はセンスも必要だと思いますが、乗り物系の運転センス、私にはないのだな、
こんなところでもしみじみ感じました。
測定板のようなところでダッシュすると時速を測ってくれますが、
走るのも苦手(お前は何が得意なんだというセルフツッコミを入れました(笑))、
なので観るだけで終了ですが、お子さん連れできたら楽しめそうです。
同じ体積でも密度が高い方が重い、ええ、このくらいなら私も理科の授業で
学んだ記憶はぼんやり残っています。
アルミニウムが一番軽い、想像していた通りでホッとしました。
で、これらの金属の横、一番左に金が置いてあったのですが、
記念に窓から手を入れてずっしりした金の重さを体験させてもらいました。
この近くに科学実験工房という部屋がありましたがその部屋の壁に、
可哀想と家に連れて帰らないでそのままにしておきましょうね、ということでしょうね。
科学ゾーン、盛りだくさんで全然飽きずにあれこれ楽しんでおりますが、
もうちょっと楽しんでから2階の宇宙ゾーンに向かいたいと思います。
(つづく)
青森旅行記2023~三沢航空科学館編④~ [日本の旅(東北)]
なんとなく自分の生きている時代に近づいてまいりました。(^-^)
羽根の部分の説明書きは右の写真に書いてありますが、
左からタービン(羽車)、燃焼室、火災検知のライン、スターター。
ワイエスジュウイチと呼んでいたのですが、正式にはワイエスイチイチ。
YS-11の名前の由来は、輸送機設計研究会輸送(Y)、設計(S)、
エンジンと機体の設計でそれぞれ1番目の案を採用したことから
「11(イチイチ)」と命名されたそうです。
第二次世界大戦後、日本は航空機の開発・製造・研究を禁止されていたそうですが
1952年(昭和27年)の解禁に伴い、国産の旅客機を製造しようという気運が高まり、
1957年(昭和32年)五戸町出身で航研機を設計された木村秀政博士(日大教授)が
技術委員長に、戦時中数々の傑作機を設計した人々が集められ、
(財)輸送機設計研究協会が設立され、1958年(昭和33年)から開発開始、
1959年(昭和34年)、日本航空機製造㈱が設立されてYS-11の開発が引き継がれ、
本格的な設計・製造が開始されました。
1962年(昭和37年)試作1号機が初飛行、1965年(昭和40年)、
初の国産実用機として国内線に就航、1973年(昭和48年)まで182機が生産され、
アメリカをはじめ世界の航空会社に採用され好評を博したそうです。
1973年まで生産されて海外にも好評を博していたのに、
この後、後継機が開発・製造されなかった理由ってなんでしょうね。
当時、私は幼稚園から小学校、という頃ですが、
その後(1976年)に金のピーナツ事件があった記憶がぼんやりあって
記憶にございません、とか、国会証人喚問で手が震えちゃったおじさん、とか、
ハチの一刺し、とか、そんなことを思い出したので、
アメリカの航空機メーカーと内閣(というか総理大臣)の密約が国内生産を
継続させないきっかけになったのかな、と思ってwikiを観ると(生産終了の項目)、
安定的な販売網が構築される前に売上が鈍化した理由として、
海外販売で強豪国並みの長期繰延低金利で対抗せざるを得ず、
第二次大戦後の国産初飛行機という実績不足で足元を観られての原価割れ販売、
初期コストに販促費などの営業関連費用を盛り込まず原価管理が杜撰、
寄せ集め集団で責任所在が不明瞭、変動相場制移行で海外販売で為替差損発生、
(1ドル=360円から円高になったら大変ですよね)
アメリカでの営業活動で代理店の不正取引が問題になり(会計監査院から指摘)、
特に海外販売分に充分な製品サポートが出来ず、欠航が相次ぐことで信頼低下し、
リース料支払い拒否され訴訟を起こされる事例(インドネシアのプラーク航空)、
などなど書いてあったのですが、モノは良くても経営が十分でないと、
適正な価格で販売して収益を上げて(お金をうまく回す)健全な経営には程遠い、
これでは生産打ち切りもやむなしなのかな、と思いました。
時節柄、タラップを上って機内を見学することができませんでした。( ノД`)
JACは日本エアコミューター(東亜国内航空と鹿児島県奄美群島が出資)で、
このルリーは奄美群島のルリカケスをイメージしたキャラクターなのでしょうね。
説明によれば、展示されているYS-11A-500型機(JA8776 製造番号2157)は、
1971年(昭和46年)5月、日本航空機製造㈱(NAMC)で製造され、
東亜国内航空で愛称「しれとこ」として就航し、2002年(平成14年)11月18日まで、
日本エアーコミューターで、鹿児島~屋久島・種子島・奄美大島・沖永良部島・
与論・福岡/福岡~高松・徳島・高知・出雲/出雲~隠岐/伊丹~隠岐の12路線を
運航し、2002年(平成14年)11月25日、31年の就航を終え、
青森県立三沢航空科学館への展示のために三沢空港に飛来したのがラストフライトと
なりました。総飛行時間は59,451時間22分、フライトサイクルは60,942回。
短距離路線が多かったと思いますが、31年間飛び続けた飛行機、お疲れ様です。
今のジャンボジェット機とは違ってどこか穏やかな感じです。
羽田から沖どめB737に乗ってきたあと、三沢でも沖どめ(風)の旅客機を
観ることが思わずニヤニヤしながら見学していたおばちゃん(私)ですが、
次は体験コーナーに進みます。
(つづく)
青森旅行記2023~三沢航空科学館編③~ [日本の旅(東北)]
航研機という名前の飛行機です。
(展示されているのはレプリカです)今回初めて知りました。
wikiから転載しますと、
航研機は東京帝国大学(現・東京大学)附置東京大学航空研究所が設計し、
飛行は大日本帝国陸軍協力のもと、1938年(昭和13年)に長距離飛行の世界記録を
作った実験機。だそうです。展示してあるのは復元機ですが、
機体は東京瓦斯電気工業(現在の日野自動車)の大森工場で製作されたそうです。
この発動機は川崎98式800馬力発動機(ハ9-Ⅱ乙)。
長距離周回飛行の世界記録樹立を目標にその達成が絶対要請であったことから、
そのために最も容易で確実な手段をとることを念頭に置いたそうです。
川崎航空機でライセンス生産していたドイツBMW開発のBMW-6(水冷Ⅴ型12気筒)を
基本に川崎航空機が独自に改良を重ねて出力を向上させた水冷・液冷エンジン系列の
最終発展型BMW-9(ハ9-Ⅱ乙)発動機。
この発動機は98式軽爆撃機(キ-32)や95式戦闘機2型改(キ-10Ⅱ改)搭載されていて
これを航研機用に改良したそうです。
戦闘機のは発動機を長距離周回飛行用に改良するポイントとしては、
・離陸時に大きな馬力が出る
・水平飛行に移ってからは燃料消費が少ない
・長時間運転に耐えられる
この3つが必須事項だったそうです。
(慶応義塾大学理工学部機会工学科から航空科学館に貸与いただいているそうです)
元々あったものを改良したのかと思っていたら、この記事を読むと形だけは残った
という大改造だったみたいで、一から作るよりはあるものを改良してということながら、
気づけば殆ど改良してしまったということなのかもしれませんね。 全体はこんな感じ(1/10縮小模型)
周回コース
右に写る男性は、操縦していた藤田雄蔵少佐(弘前出身)。
航研機の設計は木村秀政さん、製作は工藤富治さんを中心に行われたそうです。
木更津飛行場を出発して、銚子~太田~平塚(1周401.795㎞)を29周し、
世界記録を樹立したと説明に書いてありました。車輪(結構大きい)
機体に収納する完全引き込み式主脚ですが(空気抵抗を減らすため?)
離陸後、人が車輪をひっぱって収納していたそうです。(重労働だったでしょうね)ポイント通過は地上から目視
操縦席 とても狭いのですが、
飛行機の先頭にあるのかと思ったら、ここ(◎_◎;)
なので、前方が良く見えず、というか窓が小さいので外の様子を観るのが大変、
と動画で説明されていました。と心配しちゃったのですが、お酒、積んでたってー。
実際機内で呑んでいたのか分かりませんが呑んだら催しちゃうだろうし、
それ以前に飲酒運転になってしまうし、この説明、驚きました。世界記録を樹立
401.795㎞を29周、周回航続距離世界記録11,651.011㎞と、
10,000㎞コース速度世界記録186,197㎞/時の国際記録を樹立、
1938年5月13日に飛び立った航研機は翌々日の15日午後7時18分、
滞空時間62時間22分49秒で木更津飛行場に帰着しました。
狭い操縦席でほぼ3日間、操縦し続けるという荒業は今の時代にはあり得ないと
思いますが、世界記録樹立という大きな目標のために多くの人が尽力された、
ということなのだと学ぶことができました。
青森県で「銚子」の二文字を目にすることが出来たのも何かのご縁。(^-^)
続いて国産の旅客機の展示に進みましょう。(^O^)/
(つづく)
青森旅行記2023~三沢航空科学館編②~ [日本の旅(東北)]
復元した飛行機を見て(太平洋無着陸横断についても学んで)既に満足しているのですが、
このほかにも楽しい展示や体験コーナーが沢山ありました。
ミス・ビードル号がアメリカで作られた飛行機の歴史、という展示ですが、
ここからは国産飛行機の歴史が展示されています。
日本国内で最初に作られた国産飛行機はこの奈良原さんによって設計されましたが、
1号機は1910年(明治43年)10月30日、戸山ヶ原練兵場(新宿区)での滑走試験で
30㎝浮遊したものの地上を走るだけに終わってしまったため、竹製の1号機を
全木製骨格へと改良を加えた2号機として、1911年(明治44年)5月5日、
所沢飛行試験場(日本最初の飛行場)で高度約4m、距離約60mを飛び、
国産機による最初の飛行記録をつくったそうです。
ライト兄弟の初飛行から7年後の1910年、
徳川好敏大尉や日野熊蔵大尉が飛行したのが日本で最初の動力飛行とされているものの、
それはフランス、ドイツからの輸入飛行機、国産という意味では奈良原さんが設計された
飛行機が国産飛行機では初ということで、この後、国産飛行機がつくっていかれる道筋が
出来たのかなと思いました。
ただ、奈良原さんの紹介文を観たら、鹿児島の男爵家の生まれながら、飛行機開発に
私財を投じて男爵家をつぶしてしまい、一時市井に身を潜めたと書いてありました。
お金がないとこういう開発はなかなかできませんが、私財を投じて男爵家をつぶす、
今こういうところまで没頭するのは難しいかもしれませんね。
奈良原式2号隣にあった飛行機は
奈良原式2号機で操縦技術を習得し、飛行団の操縦士として奈良原式4号機鳳号で
有料飛行会や地方巡回飛行などの活動を行い、民間初の職業飛行士となった方だそうです。
青森県の出身で、地元の高等小学校を卒業後、建具職人見習いとして働きながら、
「人が乗るトンボ」づくりに励み、「野原を鳥のように飛ぶ」と吹聴していたそうですが、
その後、軍隊入りした後、上官であった徳川好敏の照会で奈良原氏に弟子入りし、
民間の飛行機養成機関(白戸協同飛行練習所)を開設、白戸式旭号や白戸式巌号(水上機)
を発注製作し、また、朝日新聞との提携で奈良原氏の門下生であった伊藤音次郎氏と
東京ー大阪を定期航路とする東西定期航空会を発足、日本の民間航空の黎明期を拓いた、
という説明が書いてあったのでほほーと読み進めていたのですが、
「東西定期航空会では事故が頻発したことから1923年(大正12年)、
37歳で航空界を退いた」と説明が書いてありました。なんだか切ない。。
野望というか大志に飛行機の性能がついていかなかったということなのだと思いますが、
乗っている人にしてみれば事故が起きるのは怖いですもんね。
ただ、こういう白戸さんのような方々のお陰で今のような安全に乗れる飛行機まで進化した、
ということなのだと思います。(今年は白戸さん引退100年後なんですね)
飛行機の特徴としては、補助翼が垂れ下がっていて風圧で水平になった補助翼を
旋回時に必要な方を引き下げる方式であることと、プロペラ軸にはずみ車をつけて
いることだそうです。高く、長く飛べるように工夫していったことがその後の飛行機の
発展につながっていったということを改めて知ることができました。
プライマリー初級用グライダー「HAYABUSA」。
昭和初期、パイロットの素質発掘のための国策として、全国の旧制中学(現在の高校)
約3000校に文部省からプライマリー(初級)グライダー「文部省一型」が配布設置、
その機体設計製作を担当した「前田グライダー」の後継者である前田健氏が
飛行距離を短く抑え簡単に浮く、子供が乗れるグライダーとして「複鷹」という名の
プライマリーグライダーを製作したそうですが、その後、前田氏の製作指導を受けた
日本宇宙少年団みさわ分団、三沢航空科学館ボランティアと職員の手により完成したのが
展示されている「HAYABUSA」で2010年10年、初飛行に成功したと書いてありました。
奈良原式、白戸式からプライマリグライダーまで観ていて思い浮かんだのが
鳥人間コンテスト、でした。(^-^;(日本テレビに刷り込まれている世代です)
戦闘機みたいに見えるけれどなんだろう、と思いながら飛行機前方に移動します。
(つづく)
青森旅行記2023~三沢航空科学館編①~ [日本の旅(東北)]
今回は思いきり見学できます。(^-^)
(三沢航空科学館ホームぺージ)https://kokukagaku.jp/
ハンガーのような雰囲気(しかも古め)にこの時点で盛り上がっております。
航空科学館、というだけあって、航空ゾーンと科学ゾーンで構成されています。
三沢駅で見かけてから知ったのですが、
三沢の淋代海岸(さびしろ)から離陸したミス・ビードル号という飛行機で、
41時間の飛行後、ワシントン州ワナッチー市に着陸した、という知識で
今回ここを訪れてもっと詳しいことを知ることができました。
(もう一人、ヒュー・ハーンドンさんも乗っています)
パネル展示とアニメでハングボーンさんが太平洋横断に成功された経緯が紹介されています。
が、それが結構紆余曲折というかトライ・アンド・エラー的な感じで面白く、
最初、世界一周最速記録に挑戦して失敗したところ、
朝日新聞が懸賞金を出すというのを知って再び太平洋横断に挑戦したというエピソード、
お金もかかるのでわかるのですが、懸賞金につられて挑戦というのが人間らしいなと
クスっと笑ってしまいました。
1931年(昭和6年)という昭和の初めも初めの話、それで青森の人たちはとても親切で
(言葉が通じていたのかも少々謎ですが)行ってらっしゃい、と見送って、
(それより小比類巻という苗字にかほる、といってしまう世代です)
その後、41時間の飛行の後、アメリカに無事着陸(胴体着陸で大変だった)、
無事アメリカに到着できたことからお礼にと、アメリカのリンゴをもって青森に行ったら、
検疫で引っかかってお世話になった人達に渡せなかったというエピソードに、
気持と反する日本(のお役所)の反応に切ない気持ちになりました。
お二人がその後パイロットとして活躍されたというエピソードの後に、
ミス・ビードル号が新たな持ち主が操縦している時に大西洋で行方不明になった、
というのが残念ながら、今回訪れた航空科学館に復刻された飛行機が展示されているのは
青森が彼らの偉業を支えたということなのかな、と思いました。
ドラム缶が沢山置いてあるのですが、200ℓ入りのドラム缶18本(3,600ℓ)を
後部座席や胴体下部に増設された燃料タンクに積み込んだそうです。
太平洋を無着陸で横断するためにこれだけの燃料がかかったということで、
この重量で飛び立つのも大変だったでしょうね。
(婆1号が生まれる前の話なので尚更そう思えてしまう)
アメリカで製作し、この航空科学館に展示されています。
三沢にこなければ知ることがなかったかもしれませんが、
三沢に来たことで知ることができた一世紀近く前に挑戦した人達、
それを支えた青森の人たちのことを知ることができました。
楽しい!
と思いながら見学は続きます。
(つづく)