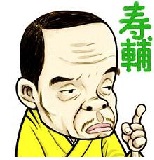京都旅行記2023~佐々木酒造で早朝酒蔵見学編③~ [日本の旅(京都)]
お米を蒸して麹菌をかけて発酵させていく過程を早足ですが見学して、
再び階下に降りると、日本酒に変わっていく過程を過ごすタンクを見学します。
-bf274.jpeg)
-2c14a.jpeg) 昭和36年?
昭和36年?
お酒って酒税がかかるので財務省の管轄なんですよね。(昔は大蔵省)
徴税しそびれないようにタンクもきちんと認可したものを使わせるってことかな。
(おそらく昭和36年は大蔵省が認可した時期なのかと思いました)
再び階下に降りると、日本酒に変わっていく過程を過ごすタンクを見学します。
-bf274.jpeg)
-2c14a.jpeg) 昭和36年?
昭和36年?お酒って酒税がかかるので財務省の管轄なんですよね。(昔は大蔵省)
徴税しそびれないようにタンクもきちんと認可したものを使わせるってことかな。
(おそらく昭和36年は大蔵省が認可した時期なのかと思いました)
-9acb1.jpeg) かき混ぜる作業 かなり重労働です
かき混ぜる作業 かなり重労働です酒母に麹、蒸米、水を加えて原酒となるもろみを約20日間かけて管理し、
麹の力によって蒸米が次第に糖化されていき、その糖を酵母菌が食べて
発酵してアルコールが生まれる。素晴らしい自然の力、といっても、
発酵を進ませるためにこうやって蔵人様が丁寧に攪拌されるのを見て、
日本酒、ありがたくいただかねばという気持が強まりました。
-b9a26.jpeg) 並行複発酵
並行複発酵上に書いたように糖化させながらアルコール発酵が同時に行われるのが
日本酒造りの特徴ということを今回学びました。
-73e32.jpeg)
-05b97.jpeg) ぶくぶく(純米吟醸)
ぶくぶく(純米吟醸)発酵が進む段階を2つのタンクで見比べることが出来ましたが、
-30749.jpeg) 毎日タンクをチェック
毎日タンクをチェック丁寧な仕事の積み重ねでお酒ができると改めて実感しました。
.jpeg) 続いて隣のエリアに移動
続いて隣のエリアに移動-8e920.jpeg) お酒を搾る機械
お酒を搾る機械実際見るのは初めてですが、このアコーディオンみたいなものをギューッと閉じると
お酒が搾れる、アイデアだなあと感心することしきりです。
これが圧搾という方法ですが、他にあと2つ方法があって、
.jpeg) 遠心分離と袋吊り
遠心分離と袋吊り-707c2.jpeg) 遠心分離器
遠心分離器獺祭さんにもある機械だそうですが、かなりお高いらしいです。
遠心力でもろみを日本酒と酒粕に分離する方法で、もろみに負荷をかけないため、
雑味のない透明感のあるお酒に仕上がる、という説明でした。
透明感のないきれいなお酒も好きなのですが、ガツンとした飲み口のお酒が
どちらかというと好きなので、遠心分離で搾られたお酒(多分高いでしょうね)は
機会があれば呑んでみたい、という程度かも。
もう一つの袋吊りはもっと高いのでこれまでも両手で足りないくらいの回数しか
呑んだことがないかな。(遠心分離と同じ、きれいなお酒で美味しいんですが)
(もろみをいれた袋を吊ってぽたぽた日本酒が垂れてくる方法なので
ものすごく時間がかかるのであまり出回らないお酒のイメージです)
-11efa.jpeg) 倉庫にやってくると
倉庫にやってくると -25fa0.jpeg)
-e8a4c.jpeg)
蔵之介さんが出演された映画作品のポスターがあっちもこっちもな感じで貼ってあって
(でも私はあまり観たことがなかったりします(^-^;)
-b4cde.jpeg) ラベル貼りに挑戦
ラベル貼りに挑戦最初に説明を聞いた会場に箱が置いてあったので??と思っていたら、
このお酒を入れるための箱だったということに気づきました。
ラベルの貼り方を聞いて「曲がっても持ち帰るのは皆さんです」という説明に
みんな笑いながら各々ラベルを貼りました。
-06c10.jpeg) 出来上がり♪
出来上がり♪ここがめちゃくちゃ寒くて(外気入りまくり)ラベルを貼ったお酒も冷たくて
持つのが大変だったのですが(急に寒くなった)この後、外に出て記念撮影です!と
蔵人様のお声かけで外に出ました。
-ad876.jpeg) 倉庫に置いてあったホワイトボード
倉庫に置いてあったホワイトボードこうやって書いてあると楽しく作業できそうですね。
-75faf.jpeg) 倉庫の外
倉庫の外見学の最初に来たところですが、もう蒸米の煙は出ていません。
-4c40f.jpeg) 杉玉を見たら左折して
杉玉を見たら左折して .jpeg)
-2a845.jpeg) はーい、うちのインスタに載せますからねー
はーい、うちのインスタに載せますからねーと言われて、え、インスタ?と思ったのですが、白衣着て頭にキャップ被って
マスクしていれば面が割れることはないか、安心して、はい、チーズ。
この後は最初に説明を聞いた会場に戻ります。
-2a838.jpeg) 朝から試飲(笑)
朝から試飲(笑)めんべい(博多土産)はいただきものですが、どうぞ、と社長が仰っていました。
-d0c56.jpeg) ラベルを貼ったお酒は箱に入れます。
ラベルを貼ったお酒は箱に入れます。 -5583c.jpeg)
-aa2b8.jpeg)
どれもしっかりした味わいですが、ガツンとまではこない感じ。
③のあらばしりは微発泡で優しい感じのお酒でした。
3種類のお酒の他に置いてあった桜色のどろっとしたのは甘酒。
ものすごい粘度、甘酒が苦手な私にはものすごく甘かったのでお菓子のように
思えて逆に美味しくいただけました。
(社長にうかがったらお菓子などの加工用に作って販売しているとのこと)
-9ab8e.jpeg) 並行複発酵についてここでも説明を聞きました
並行複発酵についてここでも説明を聞きましたビールは単行複発酵、ワインは単発酵、お酒と一口にいっても作り方が違うのだなあと
醸造、蒸留以外でも様々な方法があることを今回ちゃんと学べました。
日本酒の生産量は年々減っているそうで(コロナで更に)、かといって、
田んぼは一旦やめると戻せないのでお米を作ってもらって買っているという説明に、
若い人の(度数の高い)アルコール離れもあるのかな、と思いつつ、
度を越えない程度に美味しく日本酒を呑み続けていきたいと思いました。
8時30分終了予定が15分オーバー、丁寧なご説明を聞きながらの仕込み見学、
試飲にお土産までついて5000円であればまた参加してみたいな、と思いました。
この後、売店でお酒を何本か買ってからホテルに一旦戻ります。
(つづく)
タグ:京都