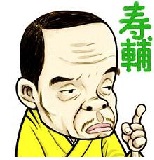京都旅行記2021秋~瑠璃光院編~ [日本の旅(京都)]
牛若丸&天狗さんの鞍馬寺の次に向かったのは瑠璃光院。
まっぷる先生掲載の写真を見て紅葉の時期に行くと素晴らしいんだろうな、
という気持はあったのですが、紅葉=大混雑という連想で近づかなかったところ。
今回は10月初旬、紅葉には程遠い時期なのでまあ入れるだろう、という軽い気持ちで
向かいました。

入口にスタッフのお兄さんが立っていて、どうぞこちらからお入りください、
と案内してくれるので迷うことはありません。
中に入って拝観料を支払いますが、2000円という強気プライス、
まあ、きれいな景色を見せていただけるので素直に支払いますが、
支払うとビニール袋を引き換えにいただきました。
パンフレットの他にクリアファイルやボールペンが入っていたのですが、
個人的にはこういうものは要らないのでお値段下げてくれるといいのにな、
でも維持するにはお金がかかるからこういう形をとっているのかも、
ある意味、特別拝観のような感じだったら妥当なのかもしれませんね。


中に進んでいくと、


ふさふさ感のある苔を見ると心が落ち着きます。(^-^)
で、瑠璃光院ですが、「そうだ 京都、行こう」のサイトから転記しますと、
比叡山の麓にある浄土真宗の寺院。
通常非公開だが、春の青もみじと秋の紅葉の時期にだけ公開される。
数寄屋造りの書院は、大正時代の終わり頃から昭和初期にかけて、
京数寄屋造りの名人と称される中村外二によって造営されたもの。
書院前には佐野藤右衛門一門の作庭と伝わる「瑠璃の庭」があり、
「瑠璃色に輝く」と表現されるほど苔の絨毯が美しい。
また庭園の紅葉が書院の机や床に映り込む様子も絶景。
境内には、三条実美命名の由緒ある茶庵「喜鶴亭(きかくてい)」や、
八瀬名物「かま風呂」の見学もできる。
まっぷる先生掲載の写真を見て紅葉の時期に行くと素晴らしいんだろうな、
という気持はあったのですが、紅葉=大混雑という連想で近づかなかったところ。
今回は10月初旬、紅葉には程遠い時期なのでまあ入れるだろう、という軽い気持ちで
向かいました。
入口にスタッフのお兄さんが立っていて、どうぞこちらからお入りください、
と案内してくれるので迷うことはありません。
中に入って拝観料を支払いますが、2000円という強気プライス、
まあ、きれいな景色を見せていただけるので素直に支払いますが、
支払うとビニール袋を引き換えにいただきました。
パンフレットの他にクリアファイルやボールペンが入っていたのですが、
個人的にはこういうものは要らないのでお値段下げてくれるといいのにな、
でも維持するにはお金がかかるからこういう形をとっているのかも、
ある意味、特別拝観のような感じだったら妥当なのかもしれませんね。
中に進んでいくと、
ふさふさ感のある苔を見ると心が落ち着きます。(^-^)
で、瑠璃光院ですが、「そうだ 京都、行こう」のサイトから転記しますと、
比叡山の麓にある浄土真宗の寺院。
通常非公開だが、春の青もみじと秋の紅葉の時期にだけ公開される。
数寄屋造りの書院は、大正時代の終わり頃から昭和初期にかけて、
京数寄屋造りの名人と称される中村外二によって造営されたもの。
書院前には佐野藤右衛門一門の作庭と伝わる「瑠璃の庭」があり、
「瑠璃色に輝く」と表現されるほど苔の絨毯が美しい。
また庭園の紅葉が書院の机や床に映り込む様子も絶景。
境内には、三条実美命名の由緒ある茶庵「喜鶴亭(きかくてい)」や、
八瀬名物「かま風呂」の見学もできる。
という説明を読むと、私が最初に歩いていたエリアは瑠璃の庭、だったのね、
と記事を書く段になってから知りました。(毎回こんな感じ)
ちなみに、10月初旬は予約なしで入れましたが、10月末あたりからは予約制で
早く予約しないといっぱいになってしまうようです。
上のサイト以外にwikiでの説明も読みましたが、
元々は田中源太郎さん(トロッコ列車の記事でも書きましたが、京都の実業家)が
所有していた土地で、建てた庵に三条実美が「喜鶴亭」と名付け、田中の死後は
京都電燈(田中源太郎がつくった会社)の重役個人の別荘となって、
その頃に、建物や庭園がつくられたそうです。
その後、京福電気鉄道(京都電燈がつくった鉄道会社)の高級料理旅館「喜鶴亭」として
営業されていましたが、廃業に伴い、岐阜市に本坊がある光明寺が買収、
本坊から寺宝を移して2005年に寺院に改められたんですね。
寺院でありながら高級料亭の面影も感じられる、そういう歴史が背景になることも
記事を書く段にしったわけですが(^-^;新緑の時期に行ってみるのも楽しそう、
という気持になりました。
と記事を書く段になってから知りました。(毎回こんな感じ)
ちなみに、10月初旬は予約なしで入れましたが、10月末あたりからは予約制で
早く予約しないといっぱいになってしまうようです。
上のサイト以外にwikiでの説明も読みましたが、
元々は田中源太郎さん(トロッコ列車の記事でも書きましたが、京都の実業家)が
所有していた土地で、建てた庵に三条実美が「喜鶴亭」と名付け、田中の死後は
京都電燈(田中源太郎がつくった会社)の重役個人の別荘となって、
その頃に、建物や庭園がつくられたそうです。
その後、京福電気鉄道(京都電燈がつくった鉄道会社)の高級料理旅館「喜鶴亭」として
営業されていましたが、廃業に伴い、岐阜市に本坊がある光明寺が買収、
本坊から寺宝を移して2005年に寺院に改められたんですね。
寺院でありながら高級料亭の面影も感じられる、そういう歴史が背景になることも
記事を書く段にしったわけですが(^-^;新緑の時期に行ってみるのも楽しそう、
という気持になりました。
(建物の中も案内するスタッフが結構多い印象でした)
景色が綺麗なところに行くと一眼レフとか巨大な望遠レンズを持って
無心に撮影している人をよく見かけて感心するのですが、
さほど混んでいないところで時間をかけて撮影するのは許容範囲ながら
これが紅葉の混雑時だったら迷惑だろうな、なんて思う邪悪な私です。
これが新緑や紅葉の時期だったら素晴らしいんでしょうね。
私のスマホでもこのくらい綺麗に見える(しかも紅葉の時期でもない)ので
料亭だったころ、このお部屋で紅葉を眺めながらお食事するなんて
贅沢な時間を過ごせる空間だったんでしょうね。
元々がお寺ではなかったのでこういう額も残っているんでしょうね。
(ということに今気づいている私です)
時節柄、中に入れないのがちょっと残念。
建物から見える高低差のあるお庭は臥龍の庭と呼ばれているそうですが、
苔が本当に活き活きとして美しいお庭でした。
これまでブログ記事で名前もわからない花の写真を掲げては
ご存じの方教えてください、とぐーたらしていたのですが、
お花の名前が分かるアプリをスマホに入れたので、
名前が分からない時はその場で調べるようになりました。(笑)
紅葉が観られなくてもこれだけの苔が観られたら私はハッピーです。
でも、紅葉の時期の光景(YouTubeでも紹介されているのでいくつか見ました)は
やはり燃えるような色が素晴らしいですね。混んでいるので行きませんが。
新緑の時期も混んでいると思いますが一度行ってみたくなりました。
と、まっぷる先生掲載の観光スポット、やっとくることが出来て満足した後は、
修学院見学までもうちょっと時間があるので寄り道してから向かいます。
(つづく)
タグ:京都